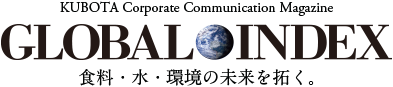開発秘話
強いけん引力を持ち、土を踏み固めにくく土にやさしいクボタパワクロ。
今では発売から20年が経ち、その性能は広く認められているが、
前輪がホイールタイヤ、後輪がおにぎり型のクローラという独特の形状もあり、
その開発は決して平坦な道のりではなかった。
パワクロはいかにして誕生したのか。その開発には長い苦労と、
農作業の負担を少しでも軽減したいという熱い思いがあった。
メーカーと販売店、そして農家とが
一体となった開発
クボタグローバルインデックス(2007年)より転載
クローラ開発に向けての試行錯誤
パワクロはどのようにして生まれ、発展したのか。その経緯を追うと、クボタならではのものづくりの工夫が凝らされていることがわかる。クボタのものづくりの強みは、農業の現場に密着し、開発中のプロトタイプを圃場に持ち込み、実際に走らせてみて農家の意見に耳を傾けるということにある。メーカーであるクボタと販売会社、そして農家との三位一体ともいえる良好な関係によりパワクロは誕生したのだ。
実は1989年から90年にかけて、日本では農場経営の大規模化が進められる中、クローラ形トラクタをクボタ以外のメーカーが相次いで発表した。ホイール形に見慣れた農家の人々にとっては新鮮に見えたことからヒット商品になっていた。農家や販売店からは「クボタは出さないのか?」「このままでは、この一帯はすべて他社になってしまう。」という声が上がった。しかし、当時、クボタはクローラ形の開発には慎重だった。というのも、クローラ形は圃場を傷めると考えていたからだ。
もっとも、ライバル会社の動きに無関心だったわけではない。市場からの強い要望を受け、営業部門を中心にしたチームがフルクローラ形やセミクローラ形などのテスト機を試作し、水田に持ち込んでは試走を行っていた。試行錯誤した結果、ようやくパワクロの原型となったテスト機が完成した。この時、岩手県の花巻にて試験走行を実施している。80馬力のトラクタにおむすび形のクローラを付けて湿田で走らせたのだ。すると、ものの5mも進まないうちにトラクタは泥の中に沈没してしまう。大失敗である。結果、社内では「やはりクローラ形は使い物にならない」という意見が大勢を占め、クローラ形開発は頓挫した。
 ㈱北海道クボタ・美瑛営業所
㈱北海道クボタ・美瑛営業所
 北海道のほぼ中央、旭川市の南東に位置する“丘のまち”美瑛町
北海道のほぼ中央、旭川市の南東に位置する“丘のまち”美瑛町
三位一体での再挑戦
その時、救いの手を差し伸べたのが、クボタの販売会社である株式会社北海道クボタの美瑛営業所の所長や社員である。「自分のところでテスト機を預からせてほしい」と申し出たのだ。中でも営業担当だった谷美史氏は知り合いの農家にテスト機を持ち込んで意見を聞いた。それが美瑛町にて広大な畑でビート(砂糖大根)などの栽培や観光農園(⇒観光農園「展望花畑 四季彩の丘」)などを幅広く手掛ける熊谷留夫氏だ。同氏は農作業のかたわら農業機械の修理や改良を自ら手掛けていた。作業場には溶接の設備などが並んでいて、さながら修理工場のようである。「プロ農家でしかもアイデアマンである熊谷氏に試作機を持ち込めば、何か問題解決の突破口が見つかるのではないか」。それが谷氏の狙いだった。

北海道クボタ・谷美史氏(左)、農家・熊谷留夫氏(右)
一方、広大な畑を持つ熊谷氏にもホイール形トラクタに対する不満があった。美瑛は傾斜地が多く、傾斜に沿って走るとトラクタが下に向かって流れてしまいがちだ。クローラ形トラクタの方が良いことはわかっていたものの、それまで試すチャンスがなかったのである。クボタから預かったテスト機はまさに渡りに船といえた。

 北海道ならではの広大なビート畑――ビートはサトウキビとならぶ砂糖の主要原料である
北海道ならではの広大なビート畑――ビートはサトウキビとならぶ砂糖の主要原料である
画期的なアイデアとなった「揺動支点」
しかし、テスト機を走らせてみると、どうも思うように走らない。特にトラクタにインプルメント(作業機)をつけて走らせると、負荷が重すぎてトラクタの前部が浮いてしまう。これではまったく使い物にならない。前浮きをなくして、安定した走りを実現するにはどうすべきか。熊谷氏と谷氏は互いにアイデアを持ち寄っては改良に向けた議論を戦わせた。営業担当でありながら、谷氏がものづくりにこだわるのには訳があった。自らも農家であり、農業の苦労はだれよりも知っていた。特に北海道における開拓の苦闘を見続けてきただけに、農家の負担を少しでも軽減できるトラクタをつくりたいという強い思いがあったのだ。その過程で出てきたのが、画期的な発明となる揺動支点である。最初にアイデアを出したのは谷氏だが、正確な計算に基づいたわけではなく、テスト機を何度も走らせているうちにイメージが浮かんだという。谷氏と熊谷氏は地元の鉄工所に頼んで、ついに揺動支点を下げたクローラをつくらせている。何度かの試作を経て、安定した走りのできるクローラが完成した。
 揺動支点を下げたテスト機の改良版1号機が、熊谷氏の農機小屋に残されていた
揺動支点を下げたテスト機の改良版1号機が、熊谷氏の農機小屋に残されていた
 傾斜地での安定性もパワクロの大きな特長のひとつだ
傾斜地での安定性もパワクロの大きな特長のひとつだ
 北海道の広大な農地では、トラクタは様々な農作業に活用される
北海道の広大な農地では、トラクタは様々な農作業に活用される
製品化へのターニングポイントとなった美瑛の大雪
1996年10月、この新しいクローラの走破性を実証する出来事が起きた。それは美瑛一帯が季節外れの大雪に見舞われた日のこと。ビートの収穫を直前にして農家の人々は慌てた。ビートは今では機械掘りが当たり前だが、雪が積もってしまうとトラクタを入れることができず、手掘りするしか方法がない。しかも広大な畑である。その時、降雪をものともせずに走る一台のクローラ形トラクタがあった。熊谷氏のトラクタである。揺動支点を下げたクローラ形のテスト機は大活躍し、無事収穫を済ますことができたのである。この出来事によって、熊谷氏と谷氏は確かな手応えを感じることとなる。その情報はさっそくクボタに伝えられた。
翌年春、揺動支点を採用したクローラ形トラクタが北海道の畑を駆け巡っていた。その走りを、クボタのトラクタ開発陣が大きな驚きをもって見入っていた。「これはいける」。傾斜地をものともしない走りの良さはそれだけインパクトがあったのだ。開発のゴーサインが出るとクボタの開発チームは一気に動いた。すぐさま試作機をつくると、新潟の圃場に持ち込んで実地テストを繰り返した。テスト結果に対する社内の評価は高かったことから、1997年、パワクロは新製品として市場に投入された。
谷氏はパワクロを世に送り出した意義について、「北海道の農業は天候に大きく左右される。降雪期間が長い上に天気が変わりやすい。そのため、農作業ができる時期は半年にも満たない。限られた時間を無駄なく使うためには効率的に作業できる機械が不可欠。それだけにパワクロは北海道の農家になくてはならないトラクタといえる」と述べている。実際、発売後、北海道ではパワクロの普及が進んでいる。北海道全体では販売されるクボタトラクタの約3割がパワクロになっている。水田向けになると4割を超えるという。

 普及が進んだ北海道のパワクロ――あちこちの農家でパワクロが見られるようになった
普及が進んだ北海道のパワクロ――あちこちの農家でパワクロが見られるようになった
新潟の農業ニーズが生んだ水田用のパワクロ
クボタが北海道の農家や販売会社とともに作り上げたパワクロ。広大な畑作の耕作用として評価は高かったものの、水田用としてはどこまで通用するか当初は未知数だった。そうした中でパワクロの魅力にいち早く着目したのが、米どころとして農業機械の性能に敏感な新潟の大規模農家だった。販売会社である株式会社新潟クボタの社長、吉田至夫氏によると「クボタが実施した実演を見て、湿田でのスムーズな走りに目を奪われた人は多かった」という。
 株式会社新潟クボタ
株式会社新潟クボタ
 株式会社新潟クボタ社長・吉田至夫氏
株式会社新潟クボタ社長・吉田至夫氏
もっとも、畑作用のパワクロがそのまま水田用として利用できるわけではない。農家からは改善を求める声が数多く寄せられた。それはパワクロを否定するのではなく、むしろ期待の大きさを表わしていた。そしてメーカーであるクボタと販売会社の新潟クボタの両社による水田用パワクロの開発が始まった。新潟クボタで営業とサービスの両方を手がけた経験を持つ前田弘一氏は、「私たちが新潟の農家の声を集めて、開発部門に伝えました。農家の方々から、あたかもご自身が開発しているかのように改良に向けてのご意見やアイデアを出していただけたことが、水田用パワクロの誕生に大きく貢献したといえます」と語っている。こうしたことはクボタと農家との長年にわたる厚い信頼関係があってこそ生まれるものにほかならない。
クボタでは農家の意見を取り入れ、改良を急ピッチで進めた。たとえば、パワクロの技術の核心である揺動支点の位置一つとってみても、畑作用と水田用では微妙に異なる。それは机上の計算で解決できるものではなく、圃場で実際に農家の人が使ってみて初めて分かることだ。また、エンジンに対して一回り大きな車体を採用し強度をアップしたり、クローラも水田用に新たに開発した。こうした改良を重ねることで、湿田でも沈むことなく、スリップもせず、しかも耕盤を傷めることのない水田用パワクロができていったのである。
パワクロの生んだ思わぬメリット
開発途上では思わぬメリットも発見された。それが田のあぜ塗りだ。縁の土を壁のように固めて水漏れを防ぐあぜ塗りは、高い技術が必要な仕事の一つとされてきた。あぜ塗り用のインプルメントが発売されていたものの、ホイール機では地面の凸凹によって車体が振られることがあり、一直線のあぜをつくるのが難しかったのである。場合によっては機械でのあぜ塗後、さらに人がスコップやクワで補修して歩かなければならず、多くの手間と時間を要した。
ところが、パワクロであぜ塗りを試したところ、直進性に優れているため驚くほど真っすぐにあぜができることがわかったのである。これだけでも農家にとっては大幅な省力化につながる。
また、吉田社長は「ホイール機と異なり、パワクロで荒起しや代かきを行った後は田植えが楽にできた」という感想を複数の農家から聞いた。これはクローラのおかげで田面が均一になるからにほかならない。ホイール形トラクタだとタイヤが30cmほど潜ってしまうため、耕盤が平らにならない。その点、パワクロのクローラの沈下は15cmほどで耕盤が平らのまま。そのため田植えが従来に比べて楽にできるという理屈だ。耕盤が安定していると、田植えやコンバインによる刈り取り作業の精度が高まり、収量の増大や安定収量にもつながる。
こうしたことが農家の間で口コミで広がり、パワクロに対する人気は一気に高まった。湿田などこれまでホイール形トラクタでは入ることができなかった圃場で、新たにパワクロを導入した農家などは「パワクロは救世主」とまで語っている。また、雪解け時の軟弱な土壌において春の農作業がいち早くできる点も農家にとっては大きなメリットであった。
新潟市内で法人組織として水稲や大豆、麦などを大規模に栽培している有限会社白銀カルチャーの社長、吉田一幸氏もまた実演を目の当たりにしてパワクロの魅力にとりつかれた一人だ。一番のメリットとしてやはりあぜ塗りを挙げている。「あぜが曲がることなく真っすぐ仕上がる。たとえ失敗してもやり直しができるので便利です」。このほか、牽引力に優れている、高速走行ができるといったメリットがあるという。「従来のトラクタは雨に弱いが、パワクロだとそれが可能になる。うちだけ作業をしていると、周囲の農家が見学に来ます」。41haもの広大な農場を経営する白銀カルチャーでは新たにトラクタの購入を予定しているが、「もちろんパワクロにしたい」と述べている。
 パワクロの技術を水田用として育てた米どころ新潟の広大な水田
パワクロの技術を水田用として育てた米どころ新潟の広大な水田
 優れた直進性でまっすぐに仕上がる「あぜ塗り」
優れた直進性でまっすぐに仕上がる「あぜ塗り」
※この記事はクボタグローバルインデックス(2007年)より転載しました。
記事の内容は全て2007年当時のものです。